Home ≫
見る ≫
福島原発事故・マーシャル諸島核実験
福島原発事故・マーシャル諸島核実験
国際シンポジウム「ビキニ事件」61年 第1部 グローバルヒバクシャの光景
核被害の現場から
ウラン鉱山−劣化ウラン−フクシマ
森瀧春子さんの話 |
|
|
WEB&YouTube配信2015年4月24日、制作:映像ドキュメント.com |
「ビキニ事件」61年の国際シンポジウムより、広島で核兵器廃絶の活動をつづけてきた森瀧春子さん(核兵器廃絶をめざすヒロシマの会共同代表、世界核被害者フォーラム事務局長)の報告。
インドのウラン鉱山、イラクの劣化ウラン弾の現場、フクシマと、実際に訪れた核被害の現場についてスライドとビデオを交え語った。
現場で起こっている健康被害、特に子どもたちの病気をとらえた映像は衝撃で、見ておくべき映像だと思う。
この11月には世界各地から核被害者を招いて世界核被害者フォーラムを準備している。
⇒世界核被害者フォーラム(http://www.fwrs.info/)2015年11月21日〜23日 広島
(荒川俊児)
28分01秒  (WMVファイル 182MB) (WMVファイル 182MB) 
28分01秒  (WMVファイル 182MB) (WMVファイル 182MB) 
※YouTubeの動画はホームページやブログに埋め込んで表示できるので、ご利用ください。
YouTube埋め込み画面の右上にある[Share]をクリックするか、YouTubeページにいって[共有]→[埋め込みコード]をクリックして出てくるコード(テキスト)をコピーして、ホームページやブログに貼り込むと、そのページでも表示できるようになります。
※リンクは、このページかトップページへ。
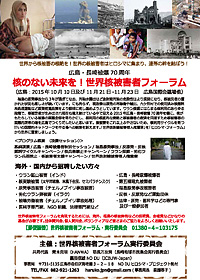 ◎世界核被害者フォーラム 2015年11月21日〜23日 広島 ◎世界核被害者フォーラム 2015年11月21日〜23日 広島
2015年、広島・長崎被爆70周年を機に、核被害の実態全容を明らかにし、核利用の根底的な廃絶と核被害者の救済をめざして開催される。国際的なネットワークをつくっていくとともに、「世界放射線被害者人権憲章」を世界に向け発したい、としている。
11月に向けて様々なプレ企画が始まっている。
詳しくは⇒世界核被害者フォーラム(http://www.fwrs.info/)
チラシ(http://www.fwrs.info/wp-content/uploads/2014/09/151010forum.pdf)
●話し手紹介
森瀧春子
もりたき・はるこ。1939年、広島市生まれ。原爆投下直前に広島県君田村(現三次市)に疎開し、被爆を免れる。広島大付属中高、広島大教育学部を卒業後、県内の公立中に行政職員として勤務。1996年に退職後、インド・パキスタンの青少年を被爆地に招くなど市民レベルの平和活動を本格化。核兵器廃絶をめざすヒロシマの会共同代表、核兵器廃絶日本市民NGO連絡会共同代表、ウラン兵器禁止国際連合(ICBUW)運営委員など国内外で活動を続ける。(『中国新聞』2011年5月23日)
  世界核被害者フォーラム実行委員会 事務局長、核兵器廃絶をめざすヒロシマの会(HANWA)共同代表、NO DU(劣化ウラン兵器禁止)ヒロシマ・プロジェクト 事務局長、ICBUW(ウラン兵器禁止国際連合)運営委員 世界核被害者フォーラム実行委員会 事務局長、核兵器廃絶をめざすヒロシマの会(HANWA)共同代表、NO DU(劣化ウラン兵器禁止)ヒロシマ・プロジェクト 事務局長、ICBUW(ウラン兵器禁止国際連合)運営委員
著書に『終わらないイラク戦争 フクシマから問い直す 』嘉指信雄・森瀧春子・豊田直巳 編(勉誠出版、2013年3月) 』嘉指信雄・森瀧春子・豊田直巳 編(勉誠出版、2013年3月)
●関連資料・関連サイト
◎国際シンポジウム「ビキニ事件」61年〈この日のこのほかの映像〉
・世界のヒバクシャ〜日米の被ばく補償(豊崎博光)(http://www.eizoudocument.com/0652toyosaki.html)
・ウラン鉱山−劣化ウラン−フクシマ(森瀧春子)(http://www.eizoudocument.com/0653moritaki.html)
・マーシャル諸島アイルック環礁の核実験被害(竹峰誠一郎、Tempo Alfred、Rosania A. Bennett)(http://www.eizoudocument.com/0654ailuk.html)
◎インド・ジャドゥゴダのウラン鉱山
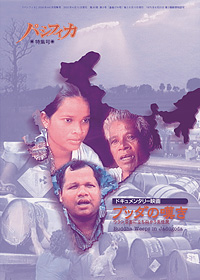 映画パンフレット『ブッダの嘆き』(PDFファイル)52ページ 映画パンフレット『ブッダの嘆き』(PDFファイル)52ページ
インド・ジャドゥゴダのウラン公害を告発したドキュメンタリー映画『ブッダの嘆き』の紹介、解説、採録シナリオなど。映画は2000年の地球環境映画祭で大賞を受賞した。
※掲載されている連絡先や住所、広告は発行時のもので、すでに無効となっていることをご了解ください。
※印刷物としても残っているので連絡いただければお送りします(1冊1000円)。
ブッダの嘆き基金(ジャドゥゴダ核被害者を支援する会)(http://www.jca.apc.org/~misatoya//jadugoda/)
小出裕章(京都大学原子炉実験所)調査報告
・〈第1回目の訪問〉苦難の先住民、インド・ジャドゥゴダ・ウラン鉱山(ノーニュークスアジアフォーラム通信、No.54、2002年2月20日)(http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/genpatu/india/nnaf-ind.pdf)
・〈第2回目の訪問〉インド・ジャドゥゴダの住民たち(ノーニュークスアジアフォーラム通信、No.64、2003年10月20日)(http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/genpatu/india/NNAF0309.pdf)
・英文の最終報告 Final report on the pollution (English version, 2004/4/27) はこちら(http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/genpatu/india.htm)から
◎劣化ウラン弾被害
ICBUW(ウラン兵器禁止国際連合)ヒロシマ・オフィス(http://icbuw-hiroshima.org/)に、ウラン兵器の人的被害の写真(豊田直巳)や出版物の紹介などがあります
●感想・コメントなどありましたらこちらからお送りください⇒ メールフォーム
〈国際シンポジウム〉「ビキニ事件」61年〜今みつめる核被害の拡がり〜
日時:2015年2月21日(土)開場10:00 10:20〜17:30
会場:明治学院大学白金校舎 本館10階大会議場
アクセス(http://www.meijigakuin.ac.jp/access/)
使用言語:日本語(マーシャル諸島の方は、英語あるいはマーシャル語を使います。英語→日本語の同時通訳があります)
参加費:無料・事前申し込み不要
プログラム:
総合司会 鴫原敦子(環境・平和研究会共同代表)
10:20- はじめに 高原孝生 (明治学院大学国際平和研究所長、国際政治学・平和研究)
10:30- 第1部 グローバルヒバクシャの光景
豊崎博光 (フォトジャーナリスト、中央大学等兼任講師)
森瀧春子 (2015年「世界核被害者フォーラム実行委員会」事務局長、核兵器廃絶をめざすヒロシマの会)
(12:00- 昼食休憩)
13:30- 第2部 マーシャル諸島 米核実験被害<非認定>地域──「視野の外」に置かれてきた人びと
竹峰誠一郎 (明星大学、グローバルヒバクシャ研究会共同代表)
Tempo Alfred (ブラボー実験のときマーシャル諸島アイルック環礁で被曝、アイルック小学校元校長、同自治体議員、70代男性)
Rosania A. Bennett (Tempoの姪、南太平洋大学法学部卒、元国会職員、日本人の祖父をもつ、40代女性)
(15:30- 休憩)
15:45- 第3部 日本漁船員1000隻をこえる被災船を追う
星正治 (広島大学名誉教授、放射線物理学、NHKスペシャル「水爆実験 60年目の真実」(2014年8月6日)で放映された共同研究よびかけ人)
高橋博子 (広島市立大学、グローバルヒバクシャ研究会共同代)
17:15- おわりに 藍原寛子 (ジャーナリスト、Japan Perspective News株式会社、福島市在住)
開催趣旨:
「ビキニ事件」から61年を迎えます。人道面に光をあてて「核なき世界」を希求する国際的な動き、あるいは東電福島第一原発事故などを視野に置きながら、被爆70年の夏を前に、国境を超える視点をもち、不可視化された核被害にどう迫っていくのか、共に考え模索し、新たな機運とつながりを築く機会にしたいと考えています。核実験場とされたマーシャル諸島から、これまで核被害が顧みられてこなかった地域の方をゲストにお迎えして開催します。
共催:明治学院大学国際平和研究所(PRIME)、グローバルヒバクシャ研究会、第五福竜丸平和協会
トヨタ財団助成プロジェクト「福島発 世界へ──世代を超え未来につなぐ被ばく体験のアーカイブ化とネットワーク構築」
問い合わせ先:
明治学院大学国際平和研究所(PRIME)(http://www.meijigakuin.ac.jp/~prime/)TEL:03-5421-5652、FAX:03-5421-5653
グローバルヒバクシャ研究会共同代表 竹峰誠一郎(明星大学)
| (c) 映像ドキュメント.com, Tokyo, Japan.
All rights reserved. |
|
|

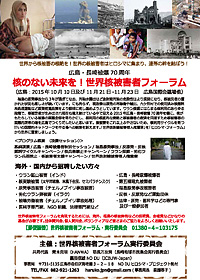

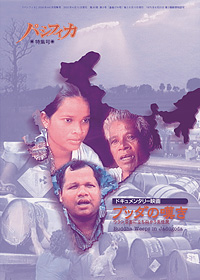 映画パンフレット『ブッダの嘆き』
映画パンフレット『ブッダの嘆き』